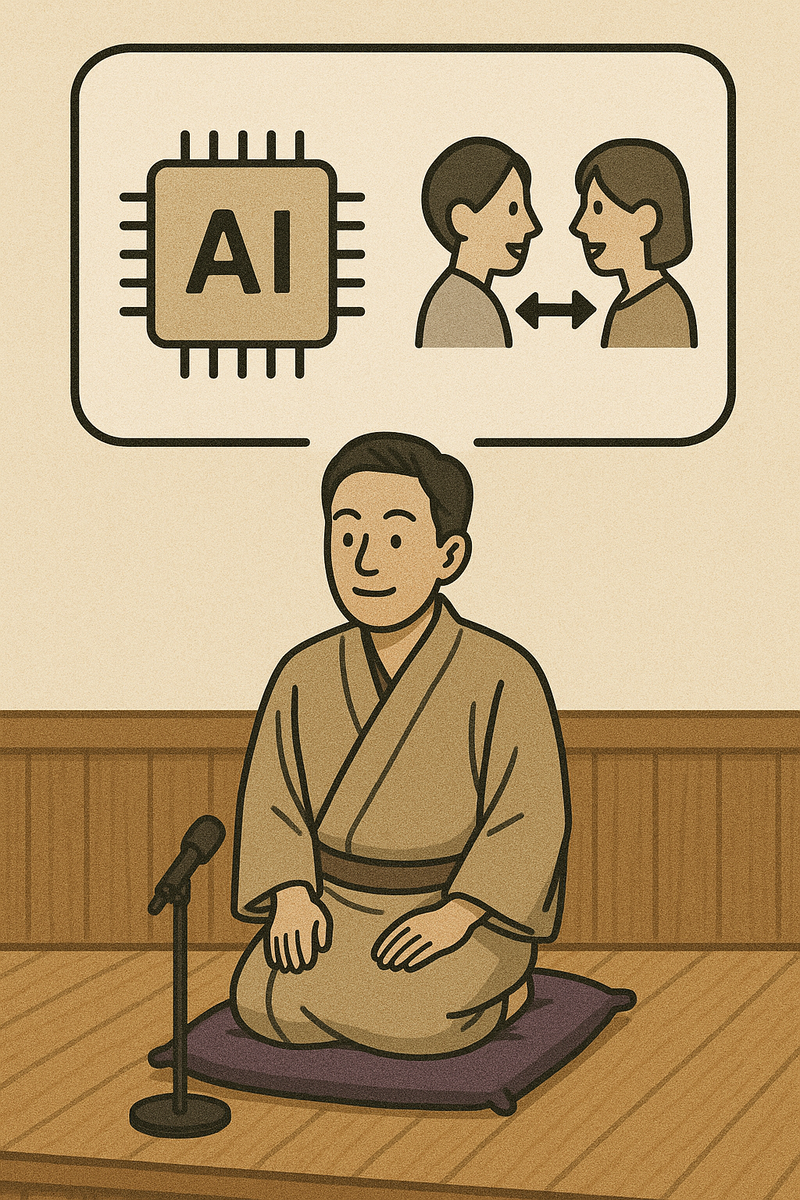
自己紹介
ラクスでPdMをしております。@keeeey_m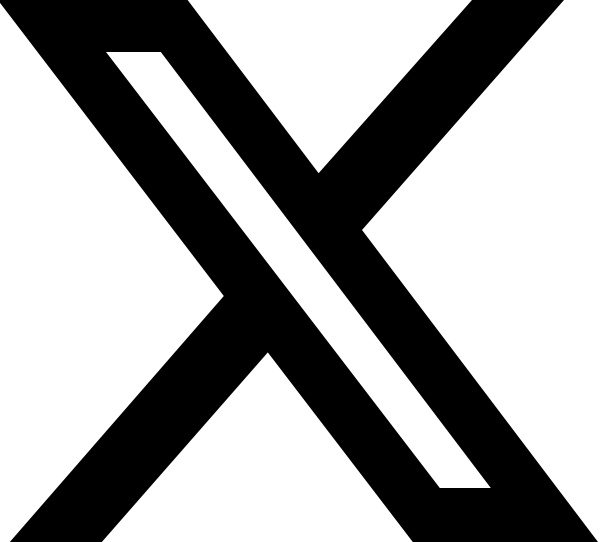 と申します。
と申します。
現在の担当商材は、楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽電子保存)を担当しており、個人としては楽楽精算×AIの担当、 楽楽明細・楽楽電子保存PdMチームのリーダーをしております。
きっかけ:毎日のテキストコミュニケーションでの葛藤
日々、業務でチャットツールを使い社内の人とテキストコミュニケーションをすることがほとんどです。ちょっとした雑談からタスクのやり取りまで、様々な情報が飛び交います。あれほど毎日テキストコミュニケーションをしていても、はっきり伝えようとすると直接すぎ、配慮して丁寧に説明しようとすると長い文面になり形式ばったものになったりと、自身が書いた文面を読み直し手が止まることがしばしばあります。
本来手軽で便利なはずなのに、なぜこうなるのか?と気になり、この事象を考察してみました。
こんな方におすすめ
- テキストコミュニケーションが苦手な方:チャットやメールで意図が伝わらず悩んでいる
- 人数の多い組織で働く方:様々な人とのやり取りで温度感の調整に困っている
- AI利用が増えている職場の方:AIとのやり取りと人間とのやり取りの使い分けに関心がある
- コミュニケーション改善を検討中のマネージャー:チーム内のテキストコミュニケーション効率化を目指している
目次
- 対面とテキストコミュニケーションの決定的な違い:情報が欠落する
- 日本特有の事象:表現が難しい言語かつ文化
- 現在のベストプラクティス:具体的なテクニック
- AI時代の新たなリスク:自然言語での対応が可能、新しい懸念要素
- 考えられる対策:使い分けが重要
- まとめ
対面とテキストコミュニケーションの決定的な違い:情報が欠落する
問題の根本は、対面コミュニケーションとテキストコミュニケーションの圧倒的な情報格差にあると、考えることができます。
感情・態度の表現
- 対面:声のトーン、表情、身振り手振りで「優しく言っている」「心配している」が伝わる
- テキスト:文字情報のみで推測するしかない
緊急度・重要度の伝達
- 対面:話すスピード、声の大きさ、間の取り方で「急いでいる」「じっくり考えてほしい」が分かる
- テキスト:同じ文面でも受け手によって解釈が変わる
確信度・断定度の表現
- 対面:声の強さ、頷き方、目線で「確信がある」「迷っている」が伝わる
- テキスト:語尾や表現に頼るしかない
関係性・距離感の調整
- 対面:物理的距離、姿勢、アイコンタクトで適切な距離感を保てる
- テキスト:敬語レベルのみで判断される
これらの情報が完全に欠落するため、送り手の意図と受け手の解釈に大きなズレが生じるのです。
日本特有の事象:表現が難しい言語かつ文化
日本のコミュニケーション文化は、テキストでの表現を特に困難にします。
「察して文化」の複雑さ
- 「空気を読む」「言わなくても分かるでしょ」が前提
- 直接的表現を避ける傾向
- 相手に配慮した遠回しな表現が好まれる
複雑な敬語システム
- 尊敬語・謙譲語・丁寧語の使い分け
- 相手との関係性や立場による表現の変化
- 「です・ます」だけでは不十分な場面の多さ
文脈依存の高さ
- 前後の会話や状況に依存する表現
- 省略が多い日本語の特性
- 同じ言葉でも文脈で意味が変わる
これらの特徴がテキストになると一気に崩れ、誤解の温床となってしまいます。
現在のベストプラクティス:具体的なテクニック
組織的にテキストコミュニケーションを改善するために、対面での豊かな表現力をテキストで再現してみても良いのかもしれません。
重要度・温度感の明示
【重要】【相談】【共有】【雑談】などの記号を活用 「心配になったので確認したいのですが」 「冗談半分ですが」 「真面目な話として」
緊急度の明確化
「急ぎ:今日中に」 「緊急ではありませんが」 「時間をかけて検討してください」 「確認だけで返信不要」
確信度の表現
「確信を持って言えるのは」 「個人的な推測ですが」 「感覚的には」 「間違いないと思います」
関係性の調整
前置き:「お疲れ様です」「心苦しいのですが」 後置き:「ご理解いただければと思います」「引き続きよろしくお願いします」
AI時代の新たなリスク:自然言語での対応が可能、新しい懸念要素
しかし、AIとの自然言語でのやり取りが可能になったことで、新たな懸念が考えられます。
AIとのコミュニケーションの特徴
- ストレートな表現で十分に意図が伝わる
- 相手の感情や反応を気にする必要がない
- 察する・察してもらう必要がない
- 効率重視で結果が出る
- 一定した反応で感情の波がない
人間とAIのやり取りを変える必要性
AIとの自然で効率的なコミュニケーションに慣れることで、以下のリスクが考えられます。
- 察る能力の衰退:AIとの「察しなくていい」やり取りに慣れ、人間同士で必要な察する能力が低下
- 直接的表現への偏り:AIとのストレートなやり取りに慣れ、人間相手でも配慮に欠ける表現をしてしまう
- 期待値のミスマッチ:AIの「完璧な理解」に慣れ、人間が理解してくれないことへのイライラが増加
- 感情への対応力低下:AIの一定した反応に慣れ、人間の気分や状況の変化に柔軟に対応できなくなる
考えられる対策:使い分けが重要
この新たなリスクに対する対策として、使い分けの重要性が浮き彫りになります。
意識的なコミュニケーションスタイルの使い分け
- AI向け:効率重視、ストレート、結果志向
- 人間向け:配慮重視、関係性考慮、感情も含めた総合的なやり取り
具体的な対策
コンテキストスイッチの習慣化
- AIとのやり取り後、人間とのコミュニケーションでは意識的にトーンを調整
定期的な振り返り
- テキストコミュニケーションで誤解が生じた事例の共有と学習
- 成功事例の蓄積と横展開
ハイブリッドアプローチ
- 重要な案件は対面またはビデオ通話を併用
- テキストだけに依存しないコミュニケーション設計
継続的なスキル維持
- 人間らしい配慮や察する能力を意識的に使い続ける
- AIに任せられることと、人間が担うべきことの区別
まとめ
難しいテキストコミュニケーションに加え、さらに自然言語でのAI利用が伴い、今後コミュニケーション力は重要な要素になり得ると考えられます。それと同時に、AIを活用することと本質は同じであるとも言えます。コミュニケーションも、AIもシンプルに考えると、情報の量と質が肝になるのは共通することです。
AI時代だからこそ、人間らしいコミュニケーション力がより価値を持つのかもしれません。効率性を追求するAIとの使い分けを意識しながら、人間同士の豊かなやり取りを大切にしていきたいものです。
AIの業務活用とかけまして、コミュニケーションととく。その心は、どちらも情報の質と量が結果を左右します。
お後がよろしいようで。
