
自己紹介
ラクスでPdMをしております。@keeeey_m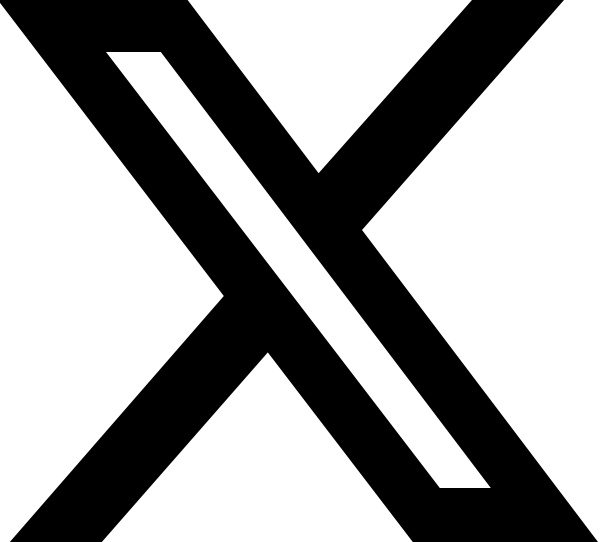 と申します。
と申します。
現在の担当商材は、楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽電子保存、楽楽債権管理)を担当しており、個人としては楽楽精算×AIの担当、楽楽明細・楽楽電子保存・楽楽債権管理PdMチームのリーダーをしております。
はじめに
最近、プロダクト開発の現場で事業成長のための指標設計について考える機会がありました。現代のビジネス環境は、技術革新の加速、市場のグローバル化、そして顧客ニーズの多様化と複雑化により、かつてないほどの速さで変化しています。
このような状況下で、単に優れた製品を開発するだけでは持続的な成長を確保することが困難になっていると感じています。従来のプロダクト開発手法では、往々にして市場の要求や顧客の潜在的な欲求を見誤り、結果としてリソースの無駄や競争力の低下を招くリスクが高まっています。
特に気になるのが、多くの企業が陥りがちな短期的な売上(PL)に直結するKPIばかりを追いかける「泥沼サイクル」です。
今回、事業成長のために不可欠な重要な考え方、「ジョブ理論(Jobs To Be Done: JTBD)」について、楽楽精算での実践を元にまとめてみました。
- 自己紹介
- はじめに
- 従来の顧客分析手法の限界
- ジョブ理論の本質的な価値
- 顧客の「片付けたいジョブ」に焦点を当てる重要性
- 予測可能なイノベーション創出のメカニズム
- 競争優位性の構築
- 製品ライフサイクルを超えた持続的イノベーション
- 実際の取り組み事例
- まとめ
従来の顧客分析手法の限界
従来のマーケティング手法は、年齢や性別といった顧客の属性(デモグラフィックデータ)や心理的特徴(サイコグラフィックデータ)を重視してきました。しかし、このアプローチには根本的な限界があります。
問題点
- 顧客の表面的な属性に依存している
- 「誰が」「何を」買うかに注目しがち
- 顧客の真の動機や状況を理解できていない
- 短期的な売上KPIに囚われやすい
「泥沼サイクル」のリスク
多くの企業が陥りがちなのが、短期的な売上(PL)に直結するKPIばかりを追いかける「泥沼サイクル」です。
泥沼サイクルの負のスパイラル

泥沼サイクルの特徴
- 新規獲得ARPU、アップセルによるNRR(Net Revenue Retention:既存顧客からの収益維持率)など短期的KPIの追求
- プロダクトの価値向上(貸借対照表に関わる活動)の後回し
- 顧客に提供できる価値の総量が変わらないまま、短期的な売上の伸び悩み
- 一度成長が止まってからの立て直しに膨大な時間と労力が必要
特にSaaSのようなビジネスモデルでは、プロダクト価値が上がらなければ遅かれ早かれ売上成長は止まり、持続的な成長が困難になります。
泥沼サイクルの影響
- 短期的KPIのみを追求した企業は、長期的に見て成長率の低下を経験することが多い
- プロダクト価値向上に投資した企業は、持続的な成長を実現しているケースが多い
- 一度泥沼サイクルに陥った企業は、脱却に相当な時間と労力を要することが一般的
ジョブ理論の本質的な価値
「誰が」「何を」から「どんな状況で」「なぜ」への視点転換
ジョブ理論(Jobs To Be Done: JTBD)は、ハーバードビジネススクールのクレイトン・クリステンセン教授が提唱した画期的な理論です。この理論の核心は、顧客が商品やサービスを購入する行為そのもののメカニズムを解き明かすことにあります。
従来の手法 vs ジョブ理論の視点転換

ジョブ理論の基本概念
- 顧客は単に商品やサービスを購入しているのではない
- 特定の状況下で「成し遂げたい進歩」、すなわち「ジョブ(用事・仕事)」を片づけるために、その商品やサービスを「雇用(消費)」する
- 「どんな状況で」「なぜ」買うのかに焦点を当てる
顧客の「片付けたいジョブ」に焦点を当てる重要性
ジョブ理論では、顧客が直面している状況と彼らが目指すべき進歩を深く理解することが重要です。
5つの重要な問い
- その人が成し遂げようとしている進歩は何か
- 苦心している状況は何か
- 進歩を成し遂げるのを阻む障害物は何か
- 不完全な解決策で我慢し、埋め合わせの行動を取っていないか
- その人にとって、よりよい解決策をもたらす品質の定義は何か、また、その解決策のために引き換え(トレードオフ)にしてもいいと思うものは何か
この視点の転換により、企業は顧客の表面的な要求ではなく、その背後にある根本的な課題や欲求を理解することができ、真に価値あるソリューションの創出へと導かれます。
予測可能なイノベーション創出のメカニズム
ジョブ理論は、イノベーションを「予測可能」にする強力なメカニズムを提供します。
予測可能性の理由
- 一時的な流行や技術の進歩に依存しない
- 人間の普遍的な「ジョブ」に根ざしている
- 顧客の「片付けたいジョブ」を発見することで、市場に新たな価値を提供
- 成熟した業界であっても、顧客に真に支持される新商品やサービスを展開可能
機能競争からの脱却
従来のプロダクト開発では、機能の多さや技術的な優位性を競争の軸としてきました。しかし、ジョブ理論の導入により、企業は機能競争から脱却し、より本質的な競争優位性を構築できます。
機能競争の限界
- 機能の多さは模倣されやすい
- 技術的優位性は時間とともに失われる
- 顧客の真のニーズから離れるリスク
- 価格競争に陥りやすい
ジョブ理論による差別化
- 顧客の「片付けたいジョブ」を深く理解
- 機能的価値を超えた情緒的・社会的価値の提供
- 顧客の状況と文脈に特化したソリューション
- 競合が模倣しにくい深い顧客ロイヤルティ
競争優位性の構築
ジョブ理論を活用した企業は、顧客の「ジョブ」解決能力そのものを競争優位性として確立できます。
競争優位性の源泉
1. 深い顧客理解
- 顧客の真の動機と状況を理解
- 表面的な要求ではなく根本的な課題を解決
- 顧客の潜在的なニーズを発見
2. 予測可能なイノベーション
- 人間の普遍的な「ジョブ」に根ざしたイノベーション
- 一時的な流行に依存しない持続的な価値創造
- 市場の変化に柔軟に対応
3. 顧客ロイヤルティ
- 顧客の感情や社会的な欲求を満たす
- 競合が模倣しにくい深い関係性を構築
- 長期的な顧客価値の向上
具体例:Appleの競争優位性
- 機能的価値: 高品質なハードウェアとソフトウェア
- 情緒的価値: 「イケている集団に属している」という感覚
- 社会的価値: 自己表現と創造性の実現
- 競争優位性: 顧客の多面的な「ジョブ」を包括的に解決する能力
事例についての補足
以下に紹介する事例は、ジョブ理論の概念を基に具体的な状況や成果を説明するために、各企業に適用した二次的な解釈や分析をしてみました。
他の事例
| 企業 | 業界 | 従来の競争 | ジョブ理論アプローチ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | 自動車業界 | 燃費、馬力、価格 | 「環境に配慮しながら、高性能な車で移動したい」 | 電気自動車市場での圧倒的なブランド価値 |
| Spotify | 音楽業界 | 楽曲数、音質 | 「いつでもどこでも、自分の好みに合った音楽を楽しみたい」 | パーソナライゼーション機能による差別化 |
| Airbnb | 宿泊業界 | 価格、立地、設備 | 「現地の人々のように生活し、ユニークな体験をしたい」 | 体験型旅行という新市場の創出 |
製品ライフサイクルを超えた持続的イノベーション
製品ライフサイクル理論(PLC)は、製品が導入期、成長期、成熟期、衰退期という段階を経ることを示唆しています。しかし、ジョブ理論の視点から見ると、顧客の「ジョブ」は製品そのものよりも普遍的で持続的です。
製品とジョブの違い
製品の特性
- 有限な寿命を持つ
- 技術の進歩により陳腐化する
- 市場の変化により衰退する
- 競合により模倣される
ジョブの特性
- 普遍的で持続的
- 人間の基本的な欲求に根ざす
- 変化の速度が遅い
- 時代を超えて存在する
具体例:「移動する」というジョブ
- 過去: 馬車 → 自動車 → タクシー
- 現在: Uber、Lyft、電動スクーター
- 未来: 自動運転車、空飛ぶ車
- 不変: 「現在地から目的地に移動する」というジョブ
市場変化への柔軟な対応
ジョブ理論を基盤とした企業は、市場の変化に柔軟に対応できます。
柔軟性の源泉
1. ジョブ中心の視点
- 製品の寿命に縛られない
- 顧客の「ジョブ」の変化を捉える
- 新たな「ジョブ」の出現を発見
2. 継続的なイノベーション
- 既存製品の改善点を発見
- 全く新しい製品カテゴリを創出
- 顧客の未解決のジョブに焦点を当てる
3. 戦略的柔軟性
- 製品が衰退期に入っても、その背後にある「ジョブ」を解決する新たなソリューションを開発
- ビジネスの継続性を確保
- 長期的な成長軌道を維持
| 企業 | 初期 | 中期 | 現在 | 不変のジョブ |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | DVDレンタルサービス | ストリーミングサービス | オリジナルコンテンツ制作 | 「質の高いエンターテイメントコンテンツを手軽に楽しむ」 |
| Microsoft | PCソフトウェア | クラウドサービス | AI・機械学習プラットフォーム | 「生産性を向上させ、仕事を効率化したい」 |
実際の取り組み事例
ジョブ理論の考え方を実際のプロダクト開発に活用した事例をご紹介します。
楽楽精算での実践
昨年度、楽楽精算のAI開発ロードマップを公開しました。製品へAIを活用していく段階で、ジョブ理論に基づき経費精算周辺の不変的な業務を整理しました。
取り組みの流れ
1. 業務に関わる人とその工程の整理
- 経費精算業務に関わる全てのステークホルダーを特定
- 不変なジョブに目を向けること
2. 重要ジョブの特定
- 経費精算における顧客の真の「片付けたいジョブ」を深く理解
- 表面的な業務効率化ではなく、根本的な課題解決に焦点
この取り組みにより、経費精算という業務における顧客の真の「ジョブ」を明確にすることができました。これにより、短期的な機能追加ではなく、顧客価値の向上に焦点を当てた持続的な成長戦略の基盤を構築できています。 しかし、このジョブだけでユーザーをわかった気にならず、一次情報を得ることが重要だと日々痛感しています。
まとめ
現代の競争が激しい市場において、プロダクト開発は単なる機能追加や技術競争に留まるべきではありません。従来の手法では、短期的な売上目標に囚われ、プロダクトの真の価値向上を見失う「泥沼サイクル」に陥るリスクがあります。
ジョブ理論の導入により、企業は顧客の真の「ジョブ」を深く理解することで、予測可能なイノベーションを創出し、持続的な競争優位性を構築できる。
これこそが、未来のビジネス成長とイノベーションを牽引する鍵となります。 次回は、組織全体の方向性を統一する鍵である「ノーススターメトリック」についてまとめたいと考えております。
