
自己紹介
ラクスでPdMをしております。@keeeey_m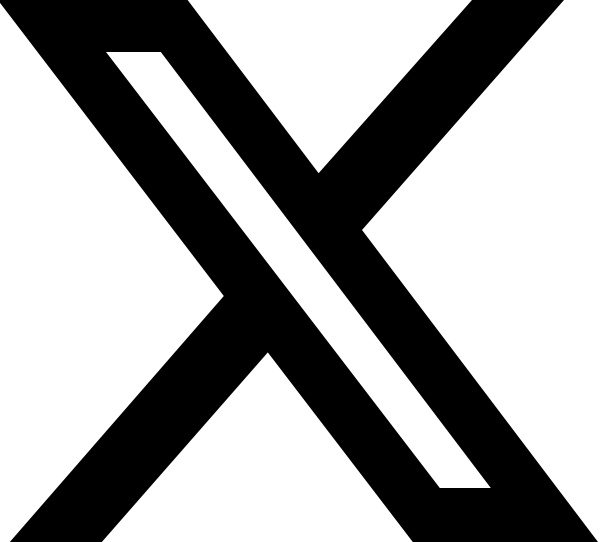 と申します。
と申します。
現在の担当商材は、楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽電子保存)を担当しており、個人としては楽楽精算×AIの担当、 楽楽明細・楽楽電子保存PdMチームのリーダーをしております。
きっかけは交流セッションのオファー
先日、アシスタントマネージャー(AM)へのステップアップを目指す女性社員向けの社内研修で話をする機会をいただきました。東京拠点で研修を受けている17名に向けて、マネジメント職として経験してきたことをざっくばらんに話してほしいとのこと。開発部門でマネジメント職として働く私の話が、彼女たちに新たな視点や気づきを与え、今後のキャリアを考える上での貴重なヒントになればという趣旨でした。
このオファーをきっかけに、自分自身のキャリアを振り返る良い機会となりました。マネジメントキャリアに前向きな気持ちがある一方で、自身が職責を果たせるのか、ライフプランと両立できるのかといった不安を感じている方々に向けて、ささやかながら私の経験をシェアしたいと思います。
偶然の積み重ねが道になる
2013年、新卒エンジニアとして入社してから10年余り。気がつけば製品管理課でチームを率いる立場になっていました。「マネジメントを目指そう」と決意した瞬間があったかと問われれば、そうではないと答えるでしょう。日々の業務に向き合い、少しずつ責任範囲が広がり、いつしかマネジメント層になっていました。
マネジメントという選択肢に興味を持ったきっかけは、ある気づきからでした。「自分が実現したい(達成したい)状態が、一個人の能力だけでは解決できない事象もある」という現実に直面したときです。
一人では解決できない課題
ラクスベトナムの立ち上げ初期、現地エンジニアの離職率の高さに悩まされていました。新たな開発拠点の構築のため、現地メンバーへのレクチャーや一緒の開発を通じて貢献しようとしましたが、教えては離職するという負のサイクルが続きました。当時は自分の能力不足を感じ、何ができたのか自問自答していました。
しかし1〜2年後、ラクスベトナムの現地マネジメント体制や採用方法が変わると、離職率は大幅に下がりました。そのとき気づいたのです。これは個人レベルでどうにかなる問題ではなかったということを。組織的な課題解決には、マネジメントという手段も必要だと考え始めたのです。
マネジメントとやりがい
「マネジメントとは、組織の目標達成のために、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報など)を効率的かつ効果的に活用し、組織の運営を最適化すること」。これを実感できるのは、一人の力では到底できないプロジェクトを成功に導けたときだと考えています。
現在進行中の楽楽精算のAI機能開発プロジェクトは、まさにその例です。自部署だけでなく部署を横断して経営資源を効率的に活用しています。何を目指しているのかを各開発部門や関連部署に説明し、理解と協力を得る。このプロセスを経て、最終的には記者会見やプレスリリースの内容にも携わるまでになりました。まだまだ始まったばかりですが、一人では決して達成できなかった成果の一つです。
強みと成長領域
ラクスには評価軸として全職種においてパフォーマンスに加えコンピテンシー(行動特性)評価があります。
ラクスのコンピテンシー
- 思考力(課題設定力・分析力 /状況判断力)
- 行動力(段取力・課題実行力/率先性・イニシアチブ)
- 人間関係力(折衝・交渉力/コミュニケーション力)
- 組織推進力(リーダーシップ・フォロワーシップ/チームワーク/人材育成)
AMやマネジメントとしての私の強みは、「思考力(課題設定力・分析力)」「行動力(段取力・課題実行力)」「コミュニケーション力(折衝・交渉力)」が挙げられます。現場で一つひとつステップを上がってきたからこそ、実務の解像度が高いのも強みです。
これらの強みは、不確実性の高い状況での意思決定と、それへのコミットメントを繰り返してきたことで培われました。意思決定をする際、必要な情報が全て揃うことはありません。それによって思いもよらぬことが起きることもあります。その結果を振り返り、「予防線は張れなかったのか」「リスクとして検討できなかったのか」「見落としていた予兆はなかったのか」と内省する。この量を繰り返し、質を上げることで、結果的に思考力と行動力が磨かれました。
また、思考力(課題設定力・分析力)と行動力(段取力・課題実行力)を活かして、折衝・交渉力にも良い影響を与えています。関連部署にはその部署の目標などがあり、どのような事業KPIを持っているかなど相手の置かれている状況を理解することで、取り組むことができています。
一方で、今後さらに成長させたい点もあります。
- コミュニケーション力:
- メンバーへの情報開示と正確な伝達
- 施策や新たな取り組みにワクワクしてもらえるような伝え方
- 伝えにくいことでも事実と解釈を区別し、誤解なく伝える力
- 組織推進力:
- リーダーシップとフォロワーシップ
- チームワーク
- 人材育成
ラベリングとの向き合い方
実は、AMになることにはかなり抵抗がありました。AMになれば、いずれマネジャーへの話は避けては通れなくなり、「女性管理職」というラベリングがつくことに違和感があったのです。ジェンダーに関係なく、一人のエンジニアとして、一人の人としてキャリアを歩み、ものづくりや課題解決に取り組む人として見られたい。
しかし、同様にラベリングに対して違和感を感じていた人の言葉を目にしました。
「いつかそういうラベルがビジネスの世界に存在しなくなってくれたらいいと思うけど、それが実現する日はきっととても遠いから、存在する前提の中でできることをやろうと思った。」
私は喜んで前に出る。
— Aki (@LoveIdahoBurger) July 22, 2023
いつかそういうラベルがビジネスの世界に存在しなくなったらいいと思うけど、それが実現する日はきっととても遠いから、存在する前提の中でできることをやろうと思うに至った次第。
そういう考え方もできるなと思い、捉え方を徐々に変えました。まだ「誰かの一歩踏み出す勇気になったら、喜んで引き受ける」という境地には至っていませんが、自分ができることをやろう、と考えるようになりました。
キャリアは一方通行ではない
キャリアは「One Way Door(一方通行)」ではありません。マネジメントにチャレンジしてみて、専門性を追求したくなったら、また意思決定すればいい。自分自身と向き合い、自分自身で意思決定をすることが大切です。
周囲の考えを汲み取る必要もなければ、無理にロールモデルを見つける必要もない。生きていく上で、世の中の様々な人の考えに触れ、自分に合うものをちょっとずつ拝借する、それだけで十分なのではないでしょうか。
日々の業務に向き合い、「もうちょっとだけやってみよう」という姿勢。そして、やるだけやってみて、また次の選択をする。そんな一歩一歩が、結果的に自分だけのキャリアを形作っていくのだと思います。
